記事内に広告を含みます

運営者(プロダクトデザイナー)
DARADARA
バイク歴7年。職業はプロダクトデザイナー。車用品メーカーで商品開発をしていた経験を生かして記事を書いています!
※記事の信憑性
カスタム・バイク用品系:プロダクトデザイナーとしての知見を使って書いています。
メンテ・整備系:『書籍』で学んだ内容をもとに書いています。
★プロフィール詳細
★記事作成に使っている書籍
★Youtube / X(Twitter)
電動バイクは普通二輪免許で乗れる?本記事では電動バイクの免許区分や車検の有無、道路交通法等のルールを警視庁に直接確認。普通自動二輪免許や大型二輪、高速道路、乗れる電動バイクの定格(W)表もあり。電動バイクに乗ろうか迷ってる人必見の内容です。
- 電動バイクは公道も走れるの?
- 原付、普通自動二輪免許で乗れる電動バイクは?
- 電動バイクで高速も走れる?車検はある?
- 大型の電動バイクが普二免許で乗れるって本当?
電動バイクに乗るには?
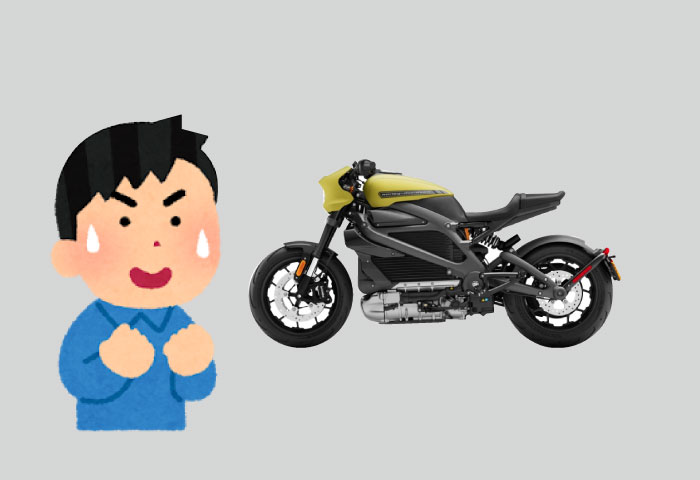
ハーレーダビットソンの参入で盛り上がる電動バイク市場。電動バイクに興味はあるけど公道で走れるの?なんて疑問に思ってるか方も多いのではないでしょうか?電動バイクも免許があれば実際に公道を走らせる事ができます。今回はそんな電動バイクのルールについて警視庁や陸運局に電話で確認した内容をまとめてみました。これから電動バイクに乗りたい!思ってる人や興味がある人は是非読んでみてください。
▼オススメの記事▼
>電動バイクはあり?注目のEVバイク10選!原付から大型まで価格やスペックも
警視庁に色々聞いてみた!

わからない事は警察に電話だ!って事で警視庁の交通相談窓口に電話しました!この記事では警視庁(陸運局もあり)の担当者の方との会話を元に作成しています。電話しすぎて今月の通話料金がやばそうですけど、、面白い情報が色々聞けたので良しとしましょう。それでは早速電動バイクに関する質問と回答を紹介していきます。
質問①:電動バイクに必要な免許は何ですか?

A. 電動バイクの定格出力によって必要な免許が変わります。
電動バイクに必要な二輪免許は下の表の通りです。ガソリン車の場合、250ccや400ccといった排気量で免許を区分していますが、電動バイクの場合は定格出力(W/ワット)で区分されます。定格0.6kW未満が原付で、0.6kW~1kWまでが原付二種、20kW未満が普通自動二輪、20kW以上だと大型自動二輪免許が必要となります。ちなみに今まで通り原付クラス(0.6kW未満)であれば自動車の免許で運転できます。
| 原付一種(※) | 原付二種 | 普通自動二輪 | 大型自動二輪 |
| 0.6kW未満 | 0.6~1kW | 20kW未満 | 20kW以上 |
質問②:法律改正前に20kW以上の電動バイク乗っていた人は?
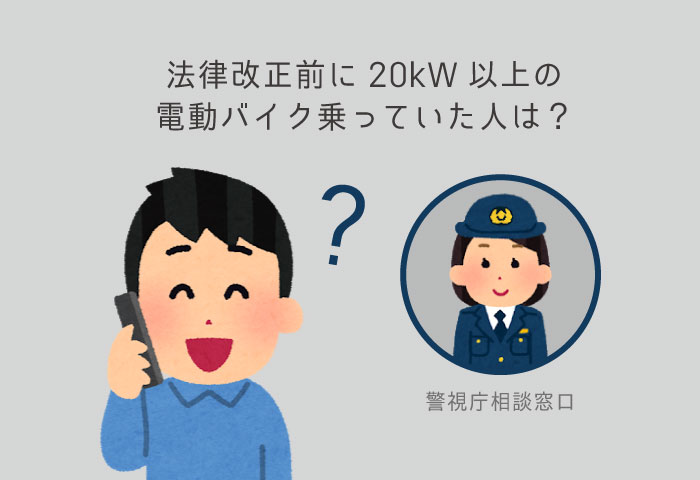
A. 2020年の12月1日までに大型自動二輪免許を取る必要があります。
2019年12月1日に道路交通法が改正され『20kW以上の電動バイクに乗るなら大型自動二輪免許』が必要になりました。改正前は普通自動二輪免許で全ての電気バイクに乗ることができましたそうです。改正前に20kW以上の電動バイクを持っていいた人は、2020年の12月1日までに普通自動二輪を取る必要があります。
対象はあくまでも法改正前に免許を持っていて、大型の電動バイクに乗っていた人です。2020年12月までは誰でも普通自動二輪で20kWの電動バイクが乗れるわけではないようなので注意
質問③:MTの電動バイクはAT限定でも運転できる?

A.いいえ、AT限定でMTの電動バイクは運転できません。
う〜んやっぱりそうですよね(笑)。クラッチ操作が伴う電動バイクについてはAT限定解除が必要だそうです。今後はカブみたいなクラッチのないATバイクが出てくる可能性もあるんでしょうかね。
質問④:高速道路を走れる定格は?

A. 定格1kW以上の電動バイクであれば高速道路を走れます。
1kW以上の電動バイクは普通自動二輪扱いになるため、高速道路の走行が可能だそうです。高速道路を走りたい人は1kW以上の電動バイクを買いましょう。ただ法律上は高速道路を走行可能ですが、充電スタンド等のインフラがまだまだ足りてないので単身の長距離巡航はちょっと不安ですね(笑)。
質問⑤:二人乗りもできる?

A. 0.6kW以上であれば問題ありません。
うんうん。このあたりは普通のバイクと同じ考え方で大丈夫だそうです。今まで通り原付(0.6kW以下)はタンデム不可。二人乗りをしたい人は0.6kW以上の二人乗り可能なバイクを買いましょう。二段階右折等も条件も同じだそうです。
質問⑥:電動バイクに車検はあるの?

A. 長さ2.5mx幅1.3mx高さ2m以下なら車検は不要です。
電動バイクの車検については、定格出力ではなく車両サイズで車検の有無が決まるそうです。長さ2.5mだとHONDAゴールドウイングクラスのサイズなので、ほとんどの電動バイクは車検が免除されることになります。これは今後電動バイク業界が盛り上がりそうな情報ですね。ただ今後電動バイクが流行ると車検必須になる可能性はあるので注意が必要です。
道路交通法の内容(興味ある人だけ)
警視庁の担当者の方に教えてもらった道路交通法の出典情報です。以下の内容はすべて上で説明したものなので、興味のある方だけ読んでみてください。言い回しがわかりにくいので、眠くなりますよ(笑)
内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
・
・
総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。
(引用:道路運送車両法施行規則第一条 から一部抜粋)
普通自動二輪:二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの
大型自動二輪:総排気量が〇・四〇〇リットルを超え、又は定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(引用:道路交通法施行規則第二条 から一部抜粋)
↑電動バイクの定格出力にまつわる道路交通法の抜粋内容
大型自動二輪車に関する規定の整備
定格出力が20.00キロワットを超える電動自動二輪車(以下「電動大型自 動二輪車」という。)を大型自動二輪車に区分することとした(府令第2 条)。 (ウ) 留意事項 改正府令の施行日前に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、電動大型 自動二輪車の運転に従事している者については、施行日から起算して1年を経過する日までの間、引き続き運転することができるほか、電動大型自動二輪車で運転免許試験を受けられることとするなど、所要の経過措置を定めた (改正府令附則第2項から第7項まで)。
(道路交通法改正)
↑2019.12に改正された電動バイク定格出力に関する道路交通法の抜粋記事
まとめ
- 電動バイクに乗るには定格別の二輪免許が必要です。
- 法改正前から普二で大型に乗ってる人は大型取得が必要
- MTの電動バイクはAT限定では運転できない
- 高速道路の走行は1kW以上の電動バイク
- 0.6kW以上のバイクならタンデムできる
- 電動バイクには実質車検がない
今回の記事をまとめると上のようになりました。電動バイクについては、警視庁でもまだまだ周知されてないみたいで、部署をたらい回しになってしまいましたが、最終的に親切な担当者の方が丁寧に教えてくれました。今年は色々と電動バイクが発売されるみたいなので楽しみですね〜。新しいバイクを買おうとしてる人は電動バイクも候補に入れてみてはいかがでしょうか?
という事で今回はここまで。最後までお読みいただきありがとうございます。






